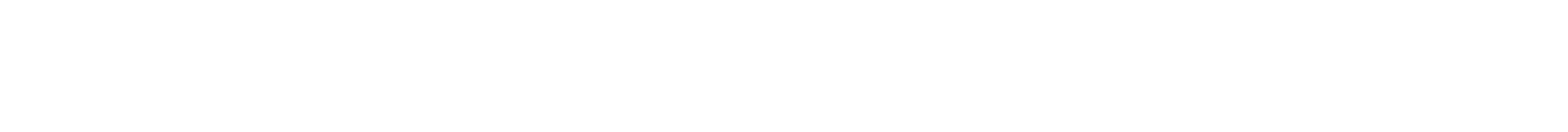山﨑千尋
俺たちはこれまでこの世界に居続ける為に一体幾つの決断をしてきただろうか。容赦無く訪れ続ける日常で、数え切れないほどの選択を掻い潜ってきた気もするし、何も選択せず、何も決定せず、ただグラス一杯の酒だけ抱いて眠りにつく夜も沢山あった気がする。多くの選択は後々考えてみると自らの体を使って、つまり五感でこの世の情報を読み解き、行動するという過程を踏んでいるように思えるが、しかしそうではない時もあるだろう。人はそれを勘や直感だと言う。俺は博打だとか競争だとかはあまりやらないのでよくわからないが、例えば将棋の上手い奴は眼前にある数多の指し手の中の90%の手は読まずに捨ててしまうらしい。長年の経験から不要な手が瞬時にわかる、理屈や言葉で了解する前に「ピンとくる」とのことだ。人間はコンピューターじゃないから、それを統計的解析って言うには無理があるよね、というのは俺にだって「ピンとくる」。人は情報をざっくりと理解することができて、それでいて、ざっくりとした情報同士をざっくりとつなぎ合わせることができる生き物なんだ。
脳死というのは人間の脳に致命的な打撃が与えられることによって脳幹を含めた全ての部位が不可逆的な機能不全を起こすことで、脳死しているにもかかわらず心配蘇生器具によって心臓は機能している状態のことを脳死現象という。脳死問題を語るには臓器移植というプラクティスな議論と激しく、複雑に衝突しなければならないが、多くの人々を悩ませているのはたった一点、「死んでいるようにみえない死」をどう扱うべきか、ということだ。なんだかおかしな話に聞こえるが全て人間が心臓死だったらこんなに人は悩むこともなかったらしい。不規則に脈打つ心臓がそれだけ人に生物の「生きてる感」を植え付けていた、ということだろう。その意味で脳死問題は人々の生への眼差し、その直感を崩してしまった。
作品を見てもらえばわかると思うんだけど、俺は脳死者遺族である。脳死者遺族は脳死者の死亡時刻を決定しなければならないという厄介な特権が与えられる。なぜなら法も医者もそれをよく理解していないからだ。あの決断の時、俺の直感は研ぎ澄まされていただろうか。今一度検討したい。俺たちは科学技術の発展によって生まれてしまった厄介な回答をこれまで直感を更新することで選択可能なものへと変化させてきたから、きっとできると思うんだ。この世界にあるあらゆる密室をつなぎ合わせて、くるくるまわる溶けない氷を伝って、親父に、なんて言葉をかけようか。